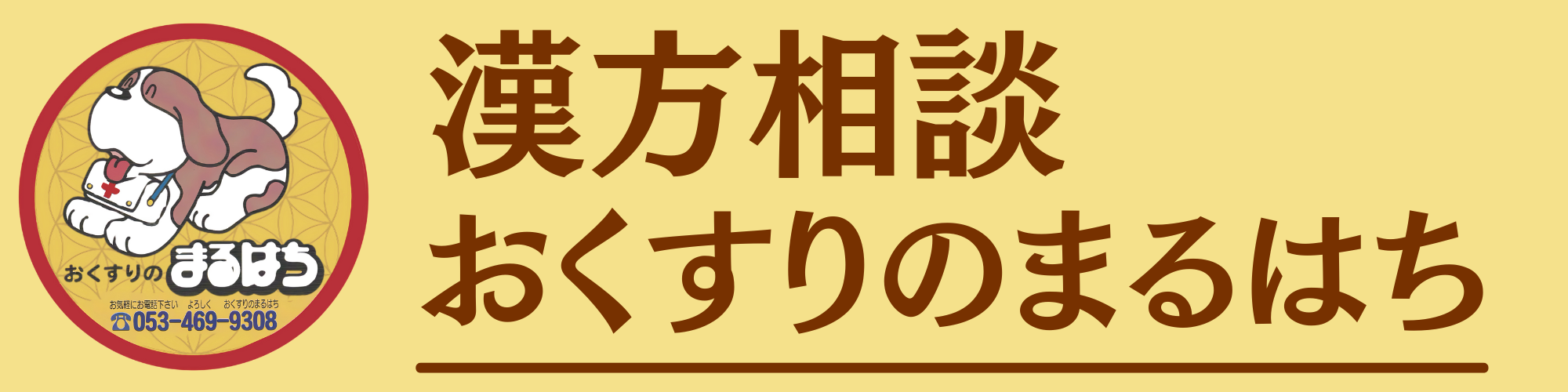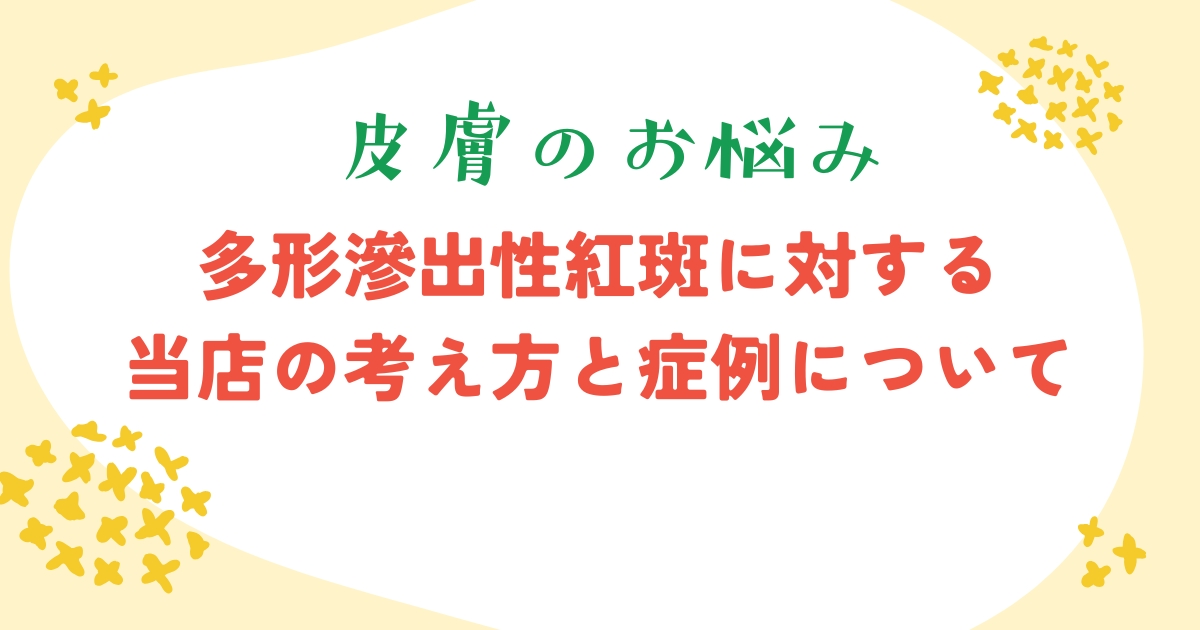多形滲出性紅斑とは?原因・症状・免疫の仕組みをわかりやすく解説
多形滲出性紅斑とは
多形滲出性紅斑(たけいしんしゅつせいこうはん)は、皮膚や粘膜に丸い紅斑(赤い発疹)が多発する病気です。紅斑の中心が少し白っぽく凹み、その周囲を赤い炎症が取り囲む「的(まと)」のような形が特徴で、時に水ぶくれや潰瘍を伴うこともあります。
一般的には数週間で自然に軽快することが多いですが、再発を繰り返すケースもあり、患者さんの生活の質を大きく下げてしまうことがあります。

「多形進出性紅斑について」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%BD%A2%E6%BB%B2%E5%87%BA%E6%80%A7%E7%B4%85%E6%96%91
多形滲出性紅斑の主な原因
多形滲出性紅斑は、感染症や薬剤、免疫の異常反応が引き金となって起こります。特に頻度が高いのが ウイルスや細菌による感染 です。
代表的な原因としては以下のものが挙げられます:
- ウイルス感染
- ヘルペスウイルス(単純ヘルペスウイルス)
- マイコプラズマウイルス
- アデノウイルス
- ヘルペスウイルス(単純ヘルペスウイルス)
- 細菌・真菌感染
- 溶連菌
- カンジダ菌
- 溶連菌
これらの病原体に感染すると、体の免疫は「抗体」という武器を作り出して戦います。抗体がウイルスや菌に結合すると「免疫複合体」が形成されます。本来ならば免疫複合体は体外に処理されるべきものですが、血管の内皮(裏打ちしている細胞層)に付着してしまうことがあります。すると免疫細胞が「敵がいる」と勘違いし、血管ごと攻撃してしまうのです。その結果、血管周囲に炎症や出血が起き、皮膚に特徴的な紅斑が現れます。
多形滲出性紅斑の特徴的な皮膚症状
多形滲出性紅斑の最大の特徴は、的のような形の紅斑です。
- 中心:白っぽく見えたり、少し陥凹している
- 周囲:赤い炎症が円形に広がる
- 全体像:火山口のように中央が凹んで周りが盛り上がった形
これは免疫複合体を中心に血管が壊され、そこから血液や炎症反応が漏れ出して広がるために起こります。単なる赤い発疹とは異なり、この「弓矢の時などの的のような形状」の紅斑は診断上の大きな手がかりとなります。輪郭がある程度しっかりとした状態の皮膚の丸型の紅斑が判別の手がかりとなります。
多形滲出性紅斑とアレルギー反応
多形滲出性紅斑はアレルギー反応の一種とも考えられています。
一般的にアレルギーと聞くと、花粉症だったり、食べ物やハウスダストなんかを思い浮かべる方が多いと思います。
ですが、実はこれらは全て1型の即時型アレルギーと呼ばれるもので、アレルギーと呼ばれる症状はこれ以外にも3つ種類があります。
アレルギー反応には大きく分けて4つの型があります。
- 即時型(I型)アレルギー
例:花粉症、食物アレルギー、ぜんそく
→ IgE抗体が関与し、ヒスタミンが大量に放出されるタイプ
アレルギーというと一番にイメージするのがこの即時型アレルギーです
- 細胞傷害型(II型)アレルギー
例:自己免疫性溶血性貧血、重症筋無力症
→ 抗体が細胞に直接結合し、細胞を壊してしまうタイプ - 免疫複合体型(III型)アレルギー
例:血清病、全身性エリテマトーデス
→ 抗体と抗原の免疫複合体が血管に沈着し、炎症を起こすタイプ - 遅延型(IV型)アレルギー
例:接触皮膚炎(湿布かぶれなど)、ツベルクリン反応
→ T細胞が関与し、数日かけて炎症が出るタイプ
多形滲出性紅斑は、このうち 「III型」と「IV型」の要素を併せ持つ」特殊な病態です。
- 感染によってできた免疫複合体が血管に沈着する(III型の特徴)
- その沈着部位をT細胞が標的とし、炎症を拡大させる(IV型の特徴)
つまり、多形滲出性紅斑は 免疫複合体による炎症 × 遅延型アレルギーの免疫攻撃 が合わさった結果として皮膚症状が出るという仕組みとなっています。
免疫複合体についてもう少し深掘り・・・
免疫複合体ってなんだか難しく、聞き覚えのない言葉ですが、
これは、抗原(ウイルスや菌)と抗体(体が作り出した武器)が結合したかたまりです。体内では常に小さな免疫複合体が作られていますが、通常は肝臓や脾臓で処理されます。
簡単なイメージをすると、矢(抗体)が刺さった落武者(抗原)が体の中にたくさん増えてしまっており、処理しきれなかったこの落武者が血管にくっついており、免疫細胞が、「まだ敵がいるぞ〜!!!」ということで攻撃をする感じのイメージです。
この落武者(免疫複合体)は基本的には肝臓や脾臓で処理されますが、感染が長引いたり免疫が過剰に働いたりすると、免疫複合体が大量に作られ処理が追いつかなくなります。
その結果、血管壁などに沈着して炎症を引き起こしてしまいます。これが多形滲出性紅斑発症の大きなメカニズムです。
当店における多形滲出性紅斑への基本的な考え方
多形滲出性紅斑は一見すると「皮膚の病気」と思われがちですが、当店では 皮膚そのものよりも体の内側にある病巣(炎症や感染の温床)を探ることが根本治療につながる と考えています。
病巣を疑う代表的なケース
- 副鼻腔炎
- 扁桃炎・咽頭炎
- 歯周病
- ヘルペスウイルスの再活性化
- カンジダ菌感染
これらの感染や炎症が体内でくすぶっていると、免疫が過剰に働き続け、免疫複合体が作られやすくなります。その結果、皮膚に多形滲出性紅斑が出てしまうのです。
問診で重視するポイント
当店ではまず、患者さんの生活背景や体質を丁寧にヒアリングします。たとえば:
- 今時点で何か体に炎症があるか
- 感染症や風邪を引いているか
- 結膜炎を繰り返し起こすか
- 耳の聞こえにくさがあるか
- 扁桃摘出の有無
- 歯科治療を継続しているか
- ワクチンの接種歴
- かつてかかった感染症との関連性
これらを丁寧に探ることで、体内に潜んでいる病巣の有無 を突き止めていきます。もし一致する症状があれば、それは「まだ免疫複合体が作られている証拠」であり、皮膚症状の根本原因を特定する大切なヒントになります。
多形滲出性紅斑の治療の第一歩
治療の基本は、体の中に潜むウイルスや菌を取り除くこと です。
- 原因菌・ウイルスの特定
→ 問診や既往歴から可能性の高い病巣を割り出す - 感染源の除去
→ 副鼻腔炎や扁桃炎の治療、口腔内環境の改善など - 免疫の安定化
→ 漢方薬や生活習慣改善で免疫機能を整える
当店では特に漢方を活用し、
- 抗菌・抗ウイルス作用のある処方
- 免疫力を高める処方
- 炎症を抑える処方
を組み合わせて使います。そうすることで、体内の病巣を取り除き、炎症を静めていけば、自然と皮膚症状も改善に向かっていきます。
代表的な処方だと、銀翹散、五味消毒飲、黄連解毒湯、柴胡清肝湯、荊芥連翹湯、温清飲、辛夷清肺湯、板藍根配合の食品、朝鮮人参の配合食品などを体調や体質に合わせて組み合わせていきます。
症例紹介:44歳女性のケースから考える多形滲出性紅斑
ここで、当店にご相談いただいたある患者さんのケースをご紹介します。
発症のきっかけと悩み
その方は 44歳の女性。
「ここ7〜8年ほど、毎年一度は多形滲出性紅斑が出て困っているんです」
と、少し疲れたような様子でご相談にこられました。
最初は年に一度ほどの発症でしたが、最近は頻度が増え、見た目もかなり悪化してしまったとのことでした。皮膚に現れる発疹だけでなく、「また出てしまった…」という気持ちも強いストレスになっていたそうです。また、皮膚科へ何度か通っていたそうですが、病名が付かなく、紅斑といったような症状名のみがつけられたそうで、病院での治療もあまりうまくいかなかったようでした。
体質と既往歴
問診を始めて、いろいろ病状について詳しくお聞きすると、元々アレルギー体質で、金属アレルギーやゴムアレルギー、大豆アレルギーなど複数のアレルギーをお持ちでした。
『多形滲出性紅斑』自体もアレルギー反応の一つ。つまり、「体の中で炎症を抱えやすい土台」を持っていることがまず問診の中から浮かび上がってきました。
他の症状と関連性
さらに問診を深めていくと、最近になって次のような症状も出ていることが分かりました。
- 目が充血しやすい
- 耳の聞こえが悪くなった
- 副鼻腔炎や喉の痛みを繰り返す
目の充血はいろいろな可能性がありますが、花粉による物理的な刺激で赤くなってしまっているのか、またアデノウイルス感染でも結膜炎を起こしやすくなっているので、喉が痛くなってしまうという点から、そういったウイルス感染の関連も頭に入れておいていました。
また、耳の聞こえにくさもいろいろな問題が考えられますが、副鼻腔炎の症状があったので、副鼻腔炎による耳管の閉塞と関係している可能性を考えました。
多形滲出性紅斑との繋がりを考えても、やはりこれらのウイルスや細菌感染が慢性的に体内でくすぶっている ことが、多形滲出性紅斑の再発を後押ししている可能性があると考えられました。
さらに深掘りした生活習慣
この女性の皮膚以外の症状(副鼻腔炎や扁桃炎)は、口の周りに起こっていることが多いので、睡眠時の呼吸についても伺うことにしました。
そうすると、やはり仰向けでは息苦しく横向きで寝ることが多いとのこと。体格もややしっかりされており、顎の下に脂肪がつきやすいタイプでした。
つまり、就寝中に 鼻が詰まりやすく、口呼吸に偏っている ことが見えてきました。
口呼吸になると口内が乾燥し、唾液による自浄作用が働かなくなります。その結果、口内で菌が増え、免疫複合体が形成されやすくなり、皮膚症状を引き起こすリスクが高まります。
また、口で呼吸をしていると、鼻の中も詰まりが起きやすくなり、菌やウイルスの温床になりやすくなってしまいます。おそらく、副鼻腔炎や、扁桃炎、歯周病など、口の周りに常に病巣を抱えており、年に数回自分の免疫が低下した時に菌やウイルスが一時的に増え、それによって免疫複合体が形成され多形滲出性紅斑を引き起こしていたのではないかということが考えられました。
改善へのアプローチ
この方に対しては、次のような方針を立てました。
- 原因菌・ウイルスを排除するための抗菌・抗ウイルス対策
→ 定期的な抗ウイルス作用や抗菌作用を示す天然成分の点鼻薬の使用で鼻腔を清潔に保ち、感染の温床を作らない - 口呼吸を改善するためのトレーニング
→ 舌や口周りの筋肉を鍛えることで、睡眠時も気道を確保しやすくする
→また体重のコントロールをして、顎下についている中性脂肪も減らしていけるように対策をすることも伝えました。
- 漢方で免疫のバランスを整える
→ 抗炎症作用と免疫調整作用を持つ処方を組み合わせる
このように 「皮膚に出ている発疹をただ抑える」のではなく、「体の内側から炎症を作っている原因を断つ」 ことを意識したアプローチを行いました。
患者さんの気持ちの変化
処方を進める中で、この女性は次第に「自分の体の中で何が起こっているのか」が理解できるようになり、不安な気持ちが和らいできたように見えました。
「今まではただ薬を塗って抑えるしかないと思っていたけど、原因にアプローチできるんですね」 と笑顔でお話しくださったのが印象的でした。
原因をしっかり探求して、一つ一つの可能性をしっかりと消していくことが遠回りのように見えて一番の近道となります。なかなか肌のトラブルが難航してしまっている方、ぜひ一度ご相談いただけたら幸いです。
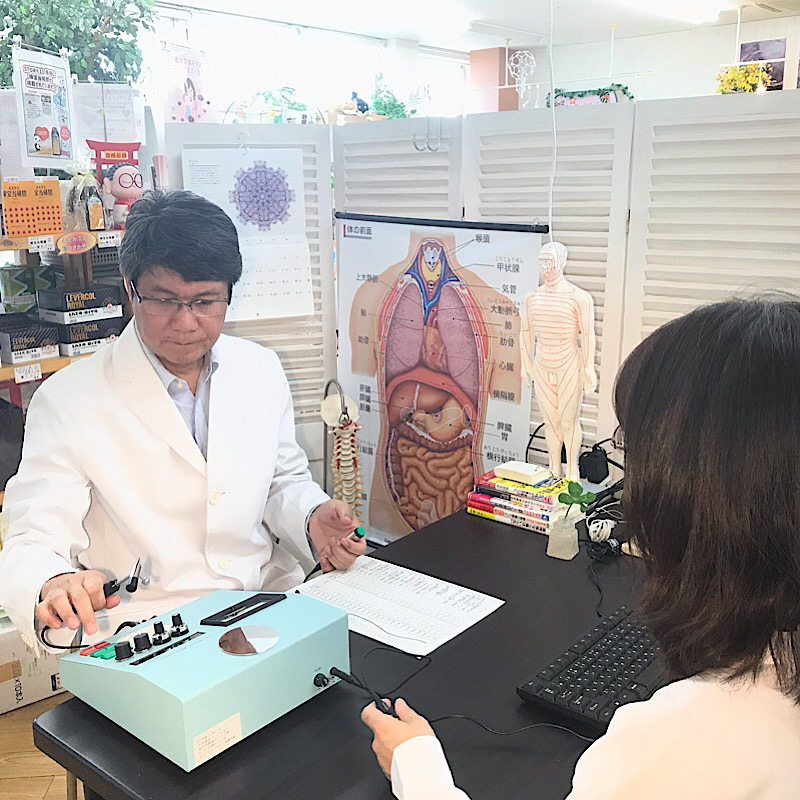
漢方相談おくすりのまるはち 店主・薬剤師 [専門資格]薬剤師、漢方相談アドバイザー、波動測定士 [経歴]相談歴36年のベテラン。代々続く薬剤師の家系に育つ。皮膚病(アトピーなど)、自律神経系の不調を得意とする。延べ1000人を超える波動測定経験を持つ。病院の設備でも見抜けない身体の不調を、漢方と波動医学の両面からアプローチし、根本原因(「根っこ」)の改善を目指します。